マイコーヒーハウス
自家焙煎珈琲販売店
SINCE 1988



※ 以下の内容は事実や歴史的裏付けではありません。

小踊りする山羊たちと山羊飼いカルディの物語
6世紀頃のエチオピア、カルディという山羊飼いの話です。ある日、アビシニア高原に住むカルディが、山羊たちを新しい牧草地に連れていくと、なぜか興奮して小踊りし、夜になっても眠ろうとしません。困ったカルディは近くにある修道院へ相談に出向きました。僧長が調べてみると、どうやら丘にある低木の赤い実を食べていることがわかりました。その実をいろいろと試して、ゆでた汁を飲んでみたところ、夜になっても眠くならなかったのです。そして、僧長は、修道院の夜の礼拝で居眠りをしてしまう僧侶たちに飲ませてみようと思いつきました。試してみると、その効果は上々。それからは、夜の礼拝があるときは、必ずこの赤い実を煎じて飲むようになり、睡魔におそわれずに修行にはげむことができるようになったそうです
いつの時代も発明は大変ユニークですが、それに勝るとも劣らないのが珈琲牛乳ではないでしょうか。牛乳を飲みやすくするために珈琲を混ぜようという思いつきは大変古いもので、大正年頃に発売された「守山珈琲牛乳」が最初のようです。この珈琲牛乳は全国の駅等で売られ、鉄道牛乳として親しまれました。戦後も昭和30年頃までありましたから、見覚えのある方もいらっしゃるかもしれません。珈琲を使ってカフェ・オ・レに近い味わいの珈琲牛乳でした。もちろん現在でも珈琲牛乳はあります。ラクトコーヒーとかコーヒー乳飲料等の名称で紙パックに入ったものが多くなりました。珈琲牛乳は今も健在です。
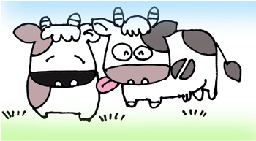

トルココーヒー(1554年頃)
煎った豆を細かく砕き(ターキッシュミル)これをイブリックという器具で煮出したもので、当然カスが浮遊しますのでそれが沈殿してから上澄みを飲むのです。飲み終えたカップに残る珈琲のカスで占いがされるようになり、これが俗にいう珈琲占いの始まりです。そもそも珈琲は最初果肉を食べたり、葉っぱや果実を煎らずに煮出して飲んでたときもありましたが、珈琲は飲用のためにいろいろな方法が試みられてきました。その歴史の中で煎った珈琲を飲むようになった最も古い方法がトルコ式の珈琲だったようです。焙煎した珈琲を細かく砕いて煮るこの方法は水と珈琲を分離しませんから黒くどろりとしたものだったようです。
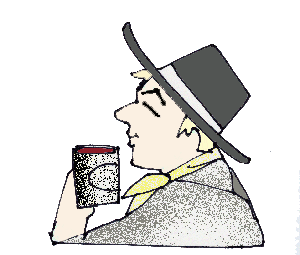
アメリカ西部開拓史の珈琲Ⅰ
アメリカンと言うと薄い珈琲を思い浮かべますが、ご存じ、アメリカの西部開拓史(1700年頃)の人たちが飲んだ珈琲は当時、濃くて、きついほど良いとされ、必需品であ りウエスタン珈琲の理想だったそうです。西へ向かう開拓者は珈琲を幌馬車に積みそして野営をするときに焚き火をしながらぐらぐら煮立った珈琲を飲んだのでした。このとき主に飲まれた珈琲は"ア-バックル"と言う銘柄が一般的でこれが無いときは麦など数々の代用品を煎って飲んだとされています。 いずれにしても、あのブリキで飲んだウエスタン珈琲は決して薄くなかったようです。
アメリカ西部開拓史の珈琲 Ⅱ
かつて、アメリカが西にのびるのに従って、珈琲も西に広がって行きました。しかし、西部では珈琲が少なく、不足していたのでした。そんなとき飲まれたの は黒パンにたんぽぽの根、どんぐり、大麦、かぎたばこなどを煮出して飲んでいたそうです。こういった代用珈琲の味は本来の珈琲とは程遠いものだったようです。珈琲のたてかたと言えば、ポットに珈琲の粉をいれてぐらぐら煮出すだけで、その粉は捨てずに水を継 ぎ足して何度も煮返すのでした。このときの珈琲の様子が「煮立ったポットに蹄鉄をほうり込んでも沈まない」とまで言われ、少しオ-バ-ですが、それほど濃い珈琲を西部開拓者達は飲んでいたと言うことです。
ブリキの珈琲とおつまみ
西部劇で皆さんご存じのブリキのカップで珈琲を飲むシ-ンをよく見ますが、1860年頃のアメリカ西部の宿屋でこんな献立があったと言います。まず、ブリキのコップに入った珈琲は勿論、ブリキの皿には、ソ-ベリ、パン、シロップ。ソ-ベリについては何だか分からないが、豆かなという気がする。それとステ-キや子羊のフライやロッキ-マウンテン・オイスタ-などとある。ロッキ-で「カキ貝」 が取れるのかとびっくりさせられるが、実はこれ、羊や牛の睾丸の事らしい、現代でもカレー味のついた料理もあるようで、当時これをバタ-焼きにしたり、焚き火の灰の中でロ-ストすると、大変美味であるらしい。ちなみに、ガラガラ蛇はチキンと良く似た味わいだとか?!


珈琲は力
予言者マホメットが重い病気にかかり、夢うつつの状態にあった時、神は天使ガブリエルを遣わされ、それまで知られていなかった食物をマホメットに与えました。それは、黒っぽく、苦く、熱のために湯気を立てていました。これを飲むと病に衰えた身体はたちまち癒されて活き活きとし、意識もはっきりしてきました。そこでマホメットはこの飲み物に(カウワ)と名づけました。カウワとはアラビア語で「力」と意味すると言われています。Cofeの言語はこのカウワという説もあります。
食後に珈琲
珈琲に含まれるカフェインは人体にさまざまな影響を与えます。最もよく知られているのが、興奮作用ですが、他に腎臓の働きを刺激して通じをよくする利尿作用があります。煙草に含まれるニコチンの毒性を弱める解毒作用があります。また、珈琲には胃の働きを活発にして消化液の分泌を促す作用があり食前酒代わりに珈琲が飲まれるぐらいです。更に、脂肪を分解する働きも見逃せません。脂肪のこってりした料理の後の珈琲は胃のもたれをとり食後をすっきりした感じにしてくれます。フルコースの後に珈琲が出るのも意味のないことではないのです。ただし、珈琲に砂糖とクリームをたっぷり入れたのでは脂肪を分解する働きも低下することになるでしょう。


芸術の店「カフェ・グレコ」
ドイツの文豪ゲーテ(1749~1832)は37歳の時、イタリアを2年ほど旅行しておりこの体験は彼の文学に大きな影響を与えたといわれています。そのゲーテが訪れたのがローマのカフェ「アンティコ・カフェ・グレコ」だったのです。この店は1760年に出来た歴史的なカフェでヴェネチアの「フローリアン」と同じく芸術家のサロンのような店でした。イタリアを舞台に「即興詩人」を書いたアルゼンチンのロッシーニやリースト、ワーグナー等の作曲家などの他、ローマにやってきた芸術家は殆どこの店に立ち寄っていると言うことです。「カフェ・グレコ」は昔の雰囲気を残したまま今でもスペイン広場の近くに店を開いているそうです。
ウィーン最初のカフェ
1683年、神聖ローマ帝国の首都であったウィーンはトルコの大軍に包囲され、陥落寸前の危機にありました。その中にゲオルグ・フランツ・コルシツキーというポーランドの兵士がいました。彼はトルコに長く生活していのでトルコの言葉や生活に精通していました。トルコの服装に身を包み、敵の包囲網を突破し友軍との連絡に成功したのです。これによってついにトルコ軍を撃退することができたのです。ウィーンの市会はこの功績を讃え『帝室の伝令』という称号を授け一軒の家を与えました。コルシツキーはトルコ軍の残していった物の中からコーヒー豆を貰い受け、ここでウィーン最初のカフェを開いたそうです。 なお、彼がトルコの服を着、コーヒーを注いでいる銅像は今でもウィーンのコルシツキー通りの一角に建っています。
